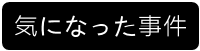森永ヒ素ミルク中毒事件とは、森永乳業の徳島工場が原因で1955年(昭和30年)に起きた大量ヒ素中毒事件のこと。
猛毒として知られるヒ素が、赤ん坊用の粉ミルクに混入されて販売されたため、1955年の6月から8月にかけて西日本一帯で乳児が下痢、嘔吐、発熱、内臓が肥大する、皮膚の変色といった症状を起こす事例が次々に報告された。
この事件は、国と企業、医療関係者が一体となって被害者を苦しめた。
報告に対する原因の究明
1955年(昭和30年)5月下旬から8月下旬にかけて、症状を発した乳児の共通点に粉ミルクで育てられたということが判明する。
岡山大学付属病院で原因を調べてみたところ、森永乳業徳島工場で作られた粉ミルクからヒ素が検出される。
1956年の厚生省の発表によれば、被害乳児は1万2,000人以上、死者は130人にも上ったという。
しかし、これだけの被害者を出したにもかかわらず、国の対応はそっけないものだった。
国は、経済を優先するためとして森永乳業側に味方し、被害者は無視される形となる。
事件の早期収拾のため、厚生労働省は、翌年に名ばかりの精密検査を行い、「後遺症なし」という結論を発表する。
厚生労働省の発表に対して被害者が各地で被災者同盟を組織し、不買運動が活発化したことから、厚生労働省は事態を収拾させるために第三者委員会を設ける。
そして、厚生労働省は、「死者は25万円、入院患者は1万円」と、一方的に補償額を決定して決着をつけようと図る。
結果を受けて被災者同盟や被害者運動も勢いが衰えていった。
被害者は、国からまともな対応をしてもらえず、また病院からもまともに相手してもらえなくなる。
森永も被害者が増えるにつれて補償額を引き下げるといった対応を取った。
次第に明らかになる後遺症
その後の調査によって、粉ミルクにヒ素が混入した原因が明らかになる。
水に溶けやすくするために入れられた「第二リン酸ソーダ」に、ヒ素が含まれていたということだった。
当時は、第二リン酸ソーダの使用に法的な規制がなく、森永側も被害者だと訴えだす始末だった。
事態が急転したのは、1969年(昭和44年)になってからだった。
大阪大学の丸山博教授らが後遺症の調査をまとめた「十四年目の訪問」を発表したことで後遺症の問題が再燃する。
被害者にとっても14年目にようやく訪れた希望の光であった。
「十四年目の訪問」によれば、8割近くの被害者は後遺症に悩まされており、ヒ素が神経、ホルモンを侵して後遺症を残しているとのことだった。
これに対して森永側は、後遺症はないと断言した。
そこで被害者と支援者は全国連絡会議を結成し、森永製品の不買運動を起こした。
森永乳製品に対する不買運動は、全国に拡がり、日本最大の不買運動にまで発展する。
当時の乳製品市場は、森永乳業がトップだったが、ヒ素事件が明るみに出たことで雪印乳業に1位の座を明け渡すこととなった。
森永ヒ素事件の裁判
森永に対する裁判は、一審では全員が無罪判決だった。
第一審の結果を受けて、検察側が上訴。
1973年(昭和48年)に森永側は刑事責任を認め、徳島工場の製造課長に対して禁固三年の判決が下った。
その後の民事訴訟では、合意によって訴えが取り下げられ、森永の全額出資により被害者の救済をするための「ひかり協会」が結成された。
現在でも森永ヒ素事件の被害者は障害で苦しんでおり、被害者に対する差別も起きている。
グリコ・森永事件
1984年(昭和59年)3月18日、江崎グリコ社長の江崎勝久氏が誘拐されるという事件が起こる。
犯人は、やがて「かい人21面相」を名乗るようになり、9月には森永製菓に対して脅迫状が届き、10月には菓子に青酸カリを入れるとの予告が届く。
犯人から届いた手紙の中には、森永ヒ素事件に触れる内容のものもあった。